親族、結婚、家族 - ポルトガル語
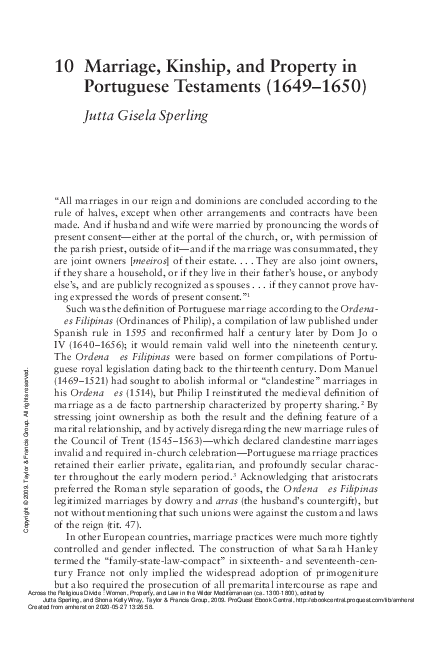
親族関係と国内グループ。 ポルトガル人は皆、親族関係を二元的に把握しているが、国内集団の構造や重視される親族関係は、地域や社会階級によって異なる。 ポルトガルの親族関係用語はラテン語にルーツがあるが、ギリシャ語ルーツの ティオ (叔父)と ティア (ポルトガル北部では、ニックネーム( アペリドス 北西部では、ニックネームは女性を介して結ばれた地域的な親族グループを識別するのに役立っている。 この地域では、ウクソリロカリティとウクソリビシナリティが好まれ、どちらも男性の移住と関連している可能性がある。ポルトガル北部の世帯は複雑で、その多くが3世代家族から構成されている。 北東部の村では、結婚後も何年も地元に住む習慣がある。 一方、ポルトガル南部では、世帯は核家族であることが多い。 友人間の義務の方が、結婚の義務よりも重要であると感じられることもある。農村の農民、特に西北部では、世帯主は夫婦が共同で務める。 パトロン そして a patroa. これとは対照的に、都市部のブルジョア層や南部では、支配的な男性の世帯主という概念がより一般的である。 洗礼式や結婚の際には、精神的な親族関係が築かれる。 親族が名付け親に選ばれることも多い( パドリニョス )であり、このような取り決めが行われる場合、名付け親と名付け子の関係が親族関係よりも優先される。
関連項目: 親族、結婚、家族 - ユダヤ人結婚。 婚姻率は20世紀に漸進的に上昇した。 婚姻年齢は空間的・時間的変動があるのが特徴で、一般に北部は南部より婚姻が遅いが、その差は徐々になくなりつつある。 南部ポルトガルでは合意による婚姻がかなり多く、北部ポルトガルは婚姻率が高い。1930年以降減少しているが、以前はポルトガル北部の農村部で非嫡出率が高かった。 ポルトとリスボンでは依然として高い。 結婚は一般的に階級内婚であり、村落でも内婚の傾向がある。 カトリック教会は伝統的に4親等以内のいとこ婚を禁じていたが(以下同様)、1930年以降、ポルトガル北部の農村部で非嫡出率が高くなっている。このような結婚は伝統的に、分割された財産を再統合するためのものであった。
関連項目: 社会政治組織 - フランス系カナダ人相続。 ポルトガルでは、1867年に制定された民法に基づき、分割相続が認められています。 ただし、親は3分の1の相続分を自由に処分することができます。 テルソ ポルトガル北部の農民では、相続は死後に行われるのが一般的であり、親は子供(多くは娘)を嫁がせることで、老後の生活保障としてテルソの約束を利用している。彼らの死後、その子供が家の所有者となる( カサ 残りの財産は相続人全員で等分する。 パルティーリャス 北部であれ南部であれ、土地の質がまちまちであるため、兄弟間の軋轢を生むことがある。 農民の中には、長期賃貸借契約を結んで土地を所有している者もいる。伝統的には、このような契約も「三生前」に一人の相続人に一括して承継され、その価値は総資産に対して計算された。 1867年の民法では、被相続人の遺産制度( ビンクロ 裕福な土地所有者は、一人の相続人が兄弟姉妹の持分を買い取ることで、財産を維持することができた。

